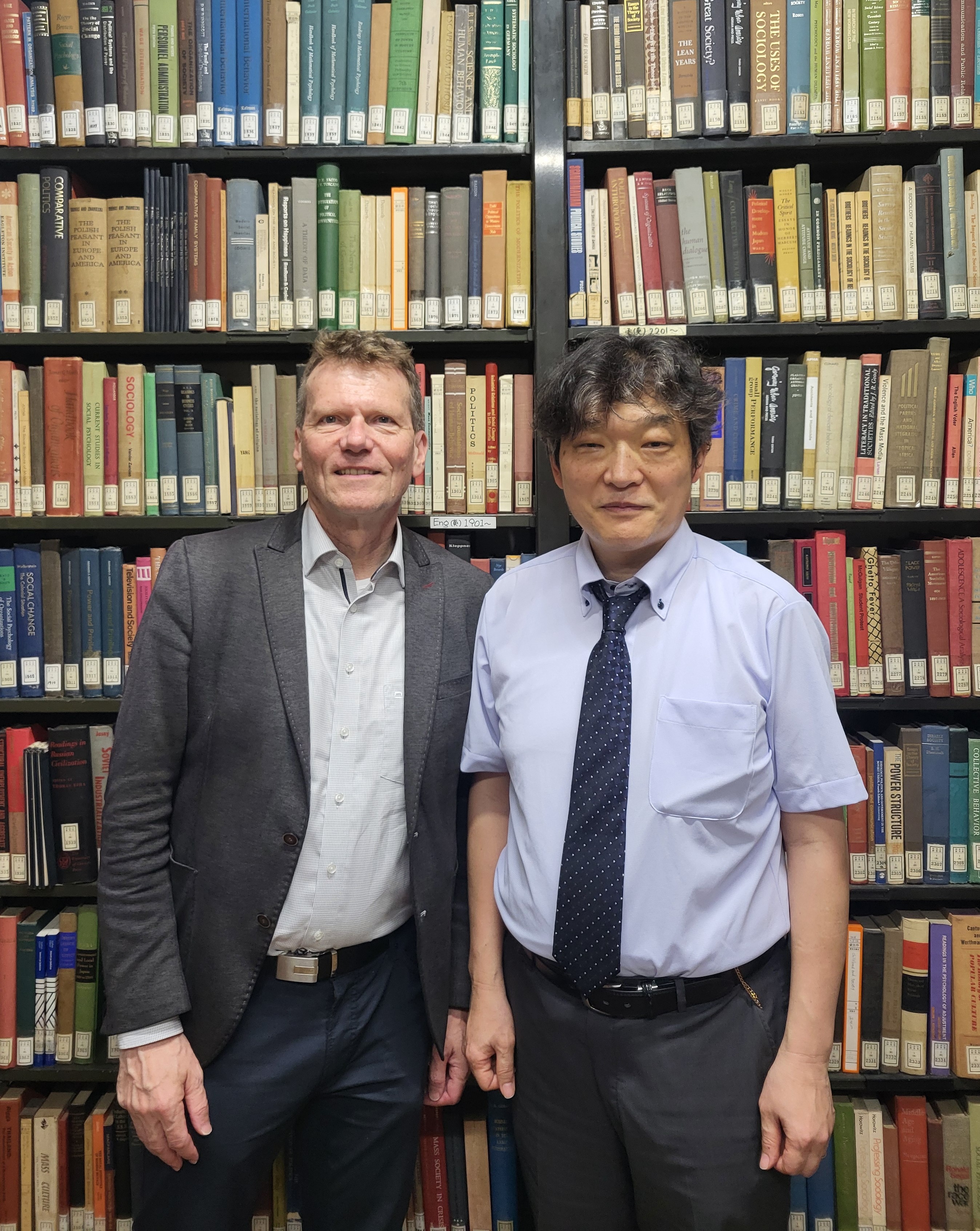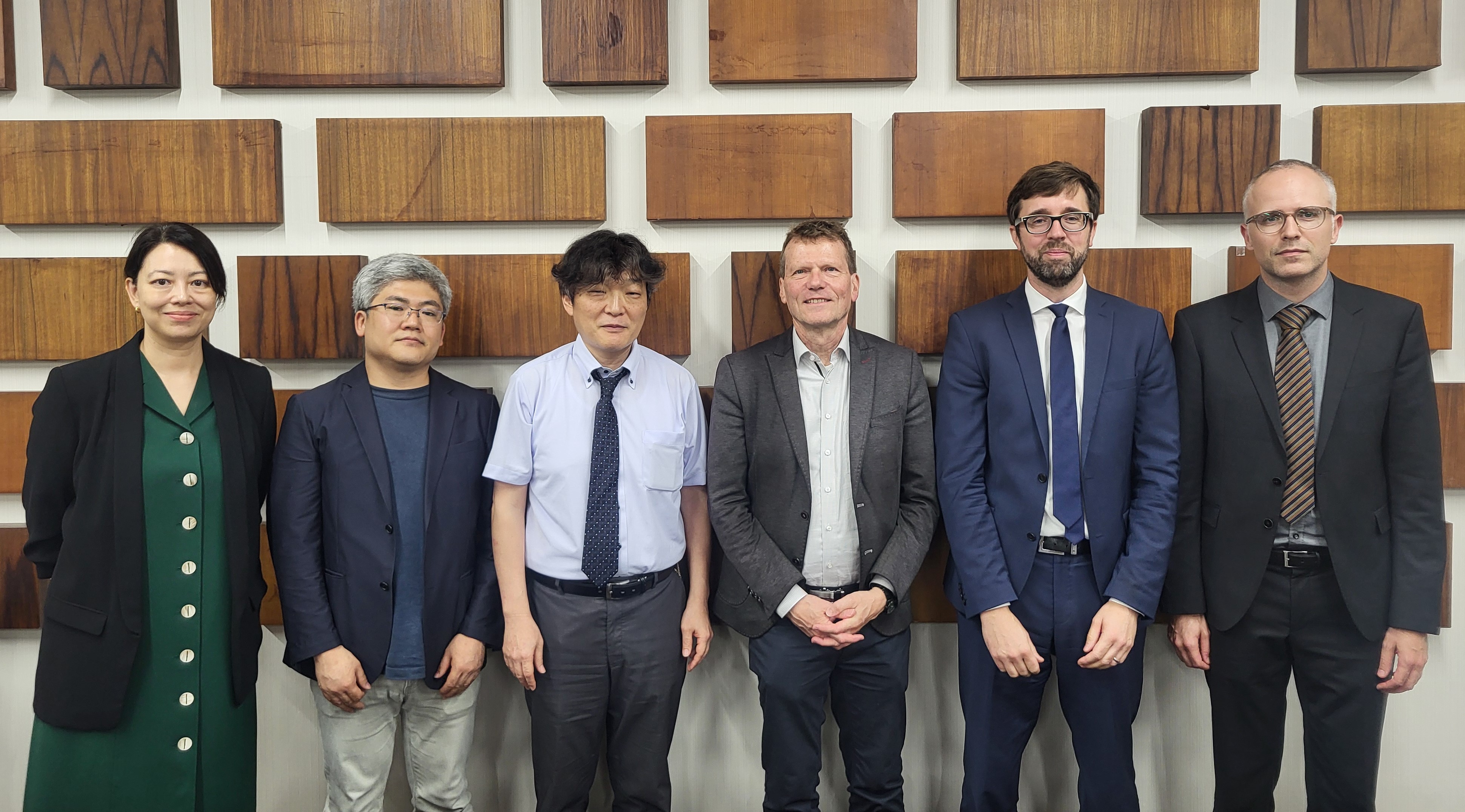DFGライプニッツ講演会 2025 東京・京都
DFGライプニッツ講演会 2025 東京・京都
イェーナ大学・エアフルト大学のハルトムート・ローザ教授(Prof. Dr. Hartmut Rosa)が2025年7月に東京と京都で「加速・疎外・共鳴―近代に関する新たな批判理論」と題した、講演を行いました。ローザ先生は社会学分野への功績が称えられ、2023年にDFGのゴットフリード・ヴィルヘルム・ライプニッツ賞を受賞されています。講演では、社会的加速の理論について概説し、どのようにして共鳴の概念が疎外を克服し、よき生に繋がりうるのかを紹介しました。
東京大学での講演会の様子
© DFG
今回、7月14日に東京大学で行われた講演会はDFGと東京大学大学院人文社会系研究科(国際人文学プロジェクト)が主催、パートナーのゲーテ・インスティトゥート東京、後援ドイツ 科学・イノベーション フォーラム 東京(DWIH東京)にて開催されました。
開会挨拶ではドイツ連邦共和国大使館 一等書記官 科学技術担当の オリヴァー・ピーパー(Dr. Oliver Pieper)氏は日本とドイツの間に築かれた学術交流の豊かな歴史について触れ、続いて東京大学大学院人文社会系研究科長・文学部長の村本由紀子教授、DFG国際交流部日本担当官のラウル・ワグナー(Raoul Wagner)が歓迎の言葉を述べました。
東京での講演会には200名を超える参加者が来場し、講演後のディスカッションでは活発な議論が交わされました。多くの質問がローザ教授の研究テーマ、加速や共鳴に関する内容で、大きな関心が反映されたものでした。
今回の講演会では、東京大学の出口剛司教授が監訳し、ゲーテ・インスティトゥートの翻訳出版助成プログラムにより2022年に出版されたローザ教授の代表的な著書『Beschleunigung. Die Veränderung der Zeitstrukturen in der Moderne』(2005)の日本語翻訳版『加速する社会―近代における時間構造の変容』が重要な役割を果たしました。
閉会挨拶の中で、ゲーテ・インスティトゥート東京の所長のメラニー・ボーノ(Melanie Bono)氏は言語の壁を越えた学術交流の重要性を強調しました。
東京に続く京都、立命館大学での講演会はDFGと立命館大学産業社会学部/社会学研究科(産業社会学部創設 60周年記念事業)との主催で、東京と同様、パートナーのゲーテ・インスティトゥート東京、後援ドイツ 科学・イノベーション フォーラム 東京(DWIH東京)で開催され、大阪・神戸ドイツ連邦共和国総領事館経済部長のヨハネス・シュヴァイツァー(Johannes Schweizer)氏、立命館大学大学院社会学社会学研究科長の市井吉興教授、DFGのラウル・ワグナーの挨拶で幕を開けました。東京での開催と同様に、講演後にはドイツ語の「Rezonanz」と「Echo」の違いなど活発な質疑応答が展開され、盛会のうちに終了しました。
東京と京都、いずれも講演会の後には懇親会が行われ、多くの参加者が最後まで意見交換、ディスカッションをする様子からはローザ教授の理論にとどまらず、ドイツの社会学研究全般への関心の高さが窺えました。